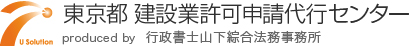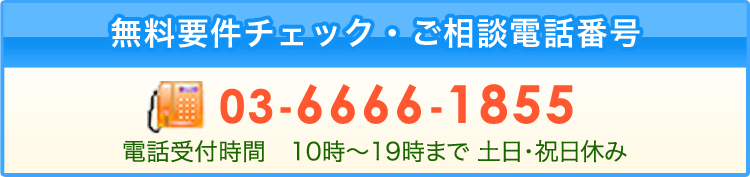建設業許可の基礎知識
建設業許可とは
元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。
許可がなくても請負える軽微な建設工事
建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
建築一式工事で下記のいずれかに該当する者
- 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
建設業許可の種類
建設業の許可は29種に分類され、
一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」
二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
を受けなければなりません。
東京都に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を請負うことは可能です。
建設業許可の有効期間
建設業許可のあった日から5年間となります。有効期間満了日は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。
許可を更新する場合は、期間が満了する30日前までに更新の手続を取らなければなりません。更新手続を取らなかった場合は、期間満了と共にその効力を失います。
建設業許可を取得するメリット・デメリット
建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが出来ません。
建設業許可を有していなくても事業を継続できる建設業者はたくさん存在しますが、それでも建設業許可を取得したい建設業者が多いのはなぜでしょうか?
ここでは、以下建設業許可を取得するメリットと取得することで生じるデメリットを紹介致します。これから建設業許可取得を検討されている方は参考にして下さい。
建設業許可取得のメリット
まず、上記で説明したように、建設業許可を取得すると、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが可能となります。
また、コンプライアンス経営が叫ばれる昨今ですから、元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の場合も少なくありません。
取引先に建設業許可を取得するよう促され取得を試みる方は非常に多いと言えます。つまり、建設業許可を取得すると取引先の確保や業務獲得の機会が増えるというメリットがあります。
建設業許可を取得するには、建設業法に沿った膨大な書類を作成し、そしてそれらの書類と申請する本人(法人)が適正な工事を請負、施工してきたことが必要となります。
つまり、建設業許可を有しているだけで、少なくとも最低限の基盤があるということをアピールすることができ、健全な経営を行ってきたことが確認することが出来ます。
融資の申請をする際も、建設業許可を有している場合と有していない場合とでは融資結果に大きく影響します。建設業許可を取得するためには一定の財産的基礎要件も必要となりますので、許可を有していれば金融機関の融資判断材料として大きな武器になると言えます。
さらに、公共工事を受注してより一層事業を安定させるためには、経営事項審査を受け、公共工事の入札に参加する必要があります。そして、それには建設業許可を取得していることが絶対条件となります。
建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることは出来ませんし、当然入札参加ができませんので、公共工事を受注することも出来ません。
このように建設業許可を取得することにより、社会的信用を得ることが出来ることはもちろんのこと、様々なビジネスチャンスを生み出すことが可能となります。
建設業許可は建設業者にとってのどから手が出るほど取得したい許可だと言えます。
建設業許可取得をすることにより生じるデメリット
デメリットと言いましても、建設業許可を取得することにより生じるメリットに比べれば些細なことです。
建設業許可を取得することにより得られるものの方が遥かに大きいので、あまりデメリットは気にされず、こういったこともあるのだなという程度でご確認下さい。
まず、建設業許可を取得するための費用が9万円~かかります。行政書士に許可取得を依頼する場合は、手続報酬として約15万円程かかります。
また、建設業許可を取得すると、年1回決算報告をしなくてはなりません。5年に一度の更新手続もしなくてはなりません。会社に変更事項が生じた場合は、変更登記に加えて建設業許可の変更手続もしなくてはなりません。
但し、大きなデメリットはこれだけです。
最初に多少の手間と費用がかかり、一定期間毎に同じく手間と費用がかかりますが、上記建設業許可を取得することにより得られるメリットに比べれば全く気にならない問題ではないでしょうか。
何かを得るためには何かを犠牲にすることが必要となる場合が多いですが、得るものに対して失うものはあまりないのが建設業許可の良いところです。
これを機にこれまで建設業許可取得を躊躇されていた方は取得を検討してみては如何でしょうか。
建設業許可の種類(29業種)
建設業の許可は以下の29業種に分類され、請負う工事の種類ごとにそれぞれ許可を受けなくてはなりません。
土木一式、建築一式の許可を持っていても、各専門の許可を持っていない場合は、500万円以上の工事を単独で請負うことは出来ません
土木一式工事
内容
- 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)をいう。
- 契約から完成引渡しまでの必要なすべての工種を含むものをいう。一部の工種の請負はそれぞれの専門工事になる。
- 複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事で、通常は二つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて社会通念上、独立の使用目的がある土木工作物を造る場合をいう。二つ以上の組合せでない場合でも、工事の規模、複雑性等から見て総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門工事として施工することが困難であると認められるものも一式工事に含まれる。
- 通常、一式工事は元請として施工されるものであるが、下水道工事等で一工区全体を一式で下請する場合など、実体としては下請であっても一式工事になる場合がある。
例示
- 道路・高速道路の新設、拡幅、改修工事(含:歩道、自転車道、側溝等の現場打ち新設工事)
- 道路への下水道本管の敷設工事:道路の掘削から管敷設、埋戻し、舗装まで全体の工程を施工するもの。(注:上水道本管のみを敷設する工事は「水道施設工事業」に該当する。)
- 橋梁・橋脚の耐震補強工事、橋梁下部の補強工事
- ダム・空港・トンネル・鉄道軌道(元請)工事を一式として請負うもの
- 区画整理・宅地・団地等造成工事(除:個人住宅造成):切土・盛土・締固め・擁壁工・排水工・防災工・道路工・舗装工・上下水道工等を総合的に施工した場合が一式工事になる。(注:掘削・切土・盛土・締固め・整地等の粗造成のみを施工する場合は「とび・土工・コンクリート工事業」に該当する。)
- 農業・灌漑水道工事を一式として請負うもの
- 道路・橋梁等、土木工作物の解体工事
建築一式工事
内容
- 原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造、解体する工事を含む)をいう。
- 複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事(要:建築確認)
例示
- 建築物の新築、増築、改築、移築
- 建築物の主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根)全体の改修を伴う工事
- ビルの一室を全面的に改造(事務所から店舗への用途変更等)、改修(解体・木工事・給排水設備・電気・内装・左官等の工事を総合的に実施)する工事
- 基地騒音対策としての(改造、改築を伴う)防音工事
大工工事
内容
- 木材の加工又は取付けにより工作物を築造する。
- 工作物に木製設備を取付ける工事
例示
- 大工工事:建築物の小規模補修工事等
- 型枠工事:木製工作物の加工・取付工事等
- 造作工事:建築物の内部造作工事等
左官工事
内容
- 工作物に壁土・モルタル・漆喰・プラスター・繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
例示
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
内容
- とび工事、ひき工事、足場の組立て等仮設工事、(機械器具・建築資材等)重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨等の組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物の解体等の工事
- くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレスコンクリート工事
- その他、基礎的ないしは準備的工事:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事
例示
- 盛土・掘削・締固め・整地等の専門工事
- ガードレール・フェンス・標識等の設置工事
- 門柱・門扉・柵・防火水槽・集水桝等の設置工事
- すべり台・ブランコ等の遊具施設や体育施設の設置工事
- 側溝工事:U字溝等、既製品を使用したもの
- 法面防護工としてのモルタル吹付、種子吹付工事
- 建方:現場における構造材の組立て工事
- 地盤改良グラウト工事:軟弱地盤を固めるため、地盤に孔を開け、薬液等を注入する工事
石工事
内容
- 石材(含:石材に類似のコンクリートブロック及び擬石)の加工、又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
例示
- 石積み(張り)工事
- コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
内容
- 瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事
例示
- 屋根ふき工事
電気工事
内容
- 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等を設置する工事
例示
- 発電設備工事
- 送配電線工事
- 引込線工事
- 変電設備工事
- 構内電気設備(含:非常用電気設備)工事
- 照明設備工事
- 電車線工事
- 信号設備工事
- ネオン装置工事(避雷針工事)
管工事
内容
- 冷暖房・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水・ガス・水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
例示
- 住宅敷地等、民地内の配管工事
- 浄化槽工事、住宅用浄化槽設置工事
- 冷暖房設備工事
- 冷凍冷蔵設備工事
- 空気調和設備工事
- 給排水・給湯設備工事
- 厨房設備工事
- 衛生設備工事
- 水洗便所設備工事
- ガス管配管工事
- ダクト工事
- 管内更生工事
- (配水小管)
タイル・れんが・ブロック工事
内容
- れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが・コンクリートブロック・タイル等を取付け、又ははり付ける工事
例示
- ALC版(軽量気泡コンクリート版パネル)取付工事
- サイディング工事(住宅用外壁パネル貼付工事)
- コンクリートブロック積み(張り)工事
- レンガ積み(張り)工事
- タイル張り工事
- 築炉工事
- スレート張り工事
鋼構造物工事
内容
- 形鋼・鋼板等の鋼材の加工、又は組立てにより工作物を築造する工事
例示
- 鉄骨工事
- 橋梁工事
- 鉄塔工事
- 石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事
- 屋外広告工事
- 閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
内容
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
例示
- 鉄筋加工組立て工事
- 鉄筋継手工事
- ガス圧接工事
舗装工事
内容
- 道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等によりほ装する工事
例示
- アスファルトほ装工事
- コンクリートほ装工事
- ブロックほ装工事
- 路盤築造工事
しゅんせつ工事
内容
- 一般的にはしゅんせつ船により河川・港湾・湖沼等の水底の土砂をさらう工事(注:水路・下水管渠等の清掃や港湾・貯水施設等の浮きゴミ収集等は該当しない。)
例示
- しゅんせつ工事
板金工事
内容
- 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
例示
- 板金加工取付け工事
- 建築板金工事
ガラス工事
内容
- 工作物にガラスを加工して取付ける工事
例示
- ガラス加工取付け工事
塗装工事
内容
- 塗装・塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は貼り付ける工事
例示
- 塗装工事
- 溶射工事
- ライニング工事
- 布張り仕上工事
- 鋼構造物塗装工事
- 路面標示工事
防水工事
内容
- アスファルト・モルタル・シーリング材等によって防水を行う工事(注:建築系の防水のみ)
例示
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
内装仕上工事
内容
- 木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・たたみ・ビニール床タイル・カーペット・ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
例示
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
機械器具設置工事
内容
- 機械器具の組立て等により、工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(注:組立て等を要する機械器具の設置工事のみ)
- それぞれの専門工事に該当しない機械器具、あるいは複合的な機械器具の設置工事が該当するため、他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に分類される。(注:工作物と一体化することなく性能を発揮する、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品を納品し、アンカーで固定するような作業は、一般的に「とび・土工・コンクリート工事業」に該当する。)
例示
- プラント設備工事
- 建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する運搬機器設置工事、立体駐車設備工事
- ガスタービンなどの内燃力発電設備工事
- トンネル・地下道等の給排気機器設置工事
- 舞台装置・遊戯施設の設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- サイロ設置工事
熱絶縁工事
内容
- 工作物、又は工作物の設備を熱絶縁する工事
例示
- 保温工事
- 冷暖房設備
- 冷凍冷蔵設備
- 動力設備、又は燃料工業
- 化学工業等の設備の熱絶縁工事
- ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事
内容
- 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
例示
- 電気通信線路設備工事
- 電気通信機械設置工事
- 放送機械設置工事
- 空中線設備工事
- データ通信設備工事
- 情報制御設備工事
- TV電波障害防除設備工事
造園工事
内容
- 整地・樹木の植栽・景石のすえ付け等により庭園・公園・緑地等の苑地を築造し、道路・建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事
例示
- 土工事を伴う樹木の植栽工事(注:植木の剪定や街路樹の枝払い等は該当しない。)
- 公園等の芝生の貼付け、客土、目土等の養生工事
- 地被工事
- 景石工事
- 地ごしらえ工事
- 公園設備工事
- 広場工事
- 園路工事
- 水景工事
- 屋上等緑化工事
さく井工事
内容
- さく井機械等を用いてさく孔・さく井を行う工事、又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
例示
- さく井工事
- 観測井工事
- 還元井工事
- 温泉掘削工事
- 井戸築造工事
- さく孔工事
- 石油掘削工事
- 天然ガス掘削工事
- 揚水設備工事
建具工事
内容
- 工作物に木製、又は金属製の建具等を取付ける工事
例示
- 金属製建具取付工事
- サッシ取付工事
- 金属製カーテンウォール取付工事
- シャッター取付工事
- 自動ドアー取付工事
- 木製建具取付工事
- ふすま工事
水道施設工事
内容
- 上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
例示
- 上水道本管敷設工事(注:道路の改修を含めて、掘削から埋戻し、舗装まで総合的に施工する場合は「土木一式工事」に該当する。)
- 水道施設工事:下水道施設については、公共下水道、及び流域下水道の処理設備の設置工事のみ該当する。(注:下水管渠の公道下配管工事は「土木一式工事」に該当し、敷地内配管工事は「管工事」に該当する。)
- 取水施設工事
- 浄水施設工事
- 配水施設工事
- 下水処理設備工事
消防施設工事
内容
- 火災警報設備、消火設備、避難設備、若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
例示
- 屋内消火栓設置工事
- スプリンクラー設置工事
- 水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体、粉末による消火設備工事
- 屋外消火栓設置工事
- 動力消防ポンプ設置工事
- 火災報知設備工事
- 漏電火災警報器設置工事
- 非常警報設備工事
- 金属製避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋、又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
内容
- し尿処理施設、又はごみ処理施設を設置する工事
例示
- ごみ処理施設工事
- し尿処理施設工事
解体工事
内容
- 工作物の解体を行う工事
例示
- 工作物解体工事
一般建設業と特定建設業の違い
元請業者として建設工事を請負い、下請けに出す場合の金額が4000万円以上(建築一式は6000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
建設工事を下請業者として受注する場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
建設工事を元請として請負った場合でも、下請けに出す金額が4000万円未満(建築一式は6000万円未満)の場合は、特定建設業の許可は不要で、一般建設業の許可で足ります。
4000万円以上(建築一式は6000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
金額は、消費税込みの契約金額で決定し、複数の業者に下請けに出す場合は、その合計金額となります。
なお、建設工事の丸投げ(一括下請け)は禁止されております。
特定建設業のうち、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、造園工事については「指定建設業」とされており、専任技術者には1級の国家資格者などを置くように義務付けられております。
建設業許可を受けるための要件
経営業務の管理責任者が常勤していること
経営業務の管理責任者の要件など詳細な説明はこちら
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
専任技術者の要件など詳細な説明はこちら
請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
- 不正な行為…請負契約の締結、履行の際の詐欺、脅迫、違法行為
- 不誠実な行為…工事内容、工期等請負契約に違反する行為
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業許可
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
※500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から「預金残高証明書」を発行して頂く必要があります。預金残高証明書は、その証明日付から1ヵ月間有効ですので、証明日付から1ヵ月以内に建設業許可申請する必要があります。通帳のコピーは不可です。
特定建設業許可
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2000万円以上あること
- 自己資本が4000万円以上あること
欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当するものは建設業許可を受けられません。
建設業許可申請書もしくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき
法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が次のような要件に該当しているとき
- 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ないもの
- 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過ないもの
- 許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しないもの
- 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
暴力団の構成員でないこと
経営業務の管理責任者とは(要件等)
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者を言います。
経営業務の管理責任者は常勤で、法人では役員でなければなりません。
※「役員」には、執行役員、監査役、会計参与等は含まれません。例えば、監査役として過去5年以上建設業に従事していたとしても、それは経営業務の管理責任者としての実務経験にはカウントされません。
また、建設業の他社の技術者及び管理技術者、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と経営業務の管理責任者を兼ねることは出来ません。但し、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることが出来ます。経営業務管理責任者と次項で説明する専任技術者は同一人物が兼ねることも可能です。※会社を清算して、代表清算人として登記されている方は、清算業務を行う必要があるため、経営業務の管理責任者に就任することは出来ません。
経営業務の管理責任者になるための要件
(イ)常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(ロ)建設業に関する経営体制を有する者(以下①と②をともに置く者)
① 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
- 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、この期間と合わせて5年以上役員等としての経験を有する者
② 上記①を直接に補佐する者で、財務管理・労務管理・業務運営の業務経験を有する者
(ハ)その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき上記(イ)又は(ロ)に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認めた者
経営業務管理責任者の確認資料 ※提出が必要です
現在の常勤性を証明するもの
- 健康保険被保険証の写し
但し、保険証に事業所名が印字されていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要になります。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書(原本提示)
- 確定申告書 法人の場合は表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
- その他
過去の経営経験を証明するもの
- 法人の役員にあっては、期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人にあっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し
- 個人にあっては確定申告書の写し(受付印押印のあるもの) 第1表と第2表
※株式会社は役員の任期がそれぞれの会社によって定められております。任期満了後の役員重任登記を怠っている場合は、役員経験をカウントすることが出来ませんのでご注意下さい。
※事業所得ではなく、給与所得として申告した確定申告書は事業者性が欠けるため不可となる可能性が高いです。事業所得と給与所得のいずれも申告している場合は、追加確認資料を求められることがあります。
上記期間の実務内容を確認する資料として以下のいずれかの資料が必要です
- 建設業許可通知書の写し
- 請負契約書、請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)
- 大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
建設業許可通知書を紛失した場合や前勤務先からコピーをもらうことができない場合は、建設業課に確認の上、申請の際、添付不要。
※請求書の場合は、請求金額が入金されたことを確認するための資料として通帳の写しを提出する必要があります(原本提示)。通帳を紛失された場合は、取扱金融機関から取引明細を期間分発行して頂ければ通帳の替わりになります。但し、金融機関によっては、過去数年分までしか発行出来ない場合もありますので、取扱金融機関に事前に確認して下さい。
※発注書のコピーなどで、従前の会社から原本を借りることができない場合、予め審査担当に相談の上、コピーのみで受理して頂けるケースもございます。
※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談下さい。
経営業務管理責任者に準ずる地位に基づく申請要件
経営業務管理責任者の要件に関しては、経営業務の管理責任者とはをご参照頂きたいのですが、経営業務管理責任者の要件の中で「許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、その経験を有する者」という要件があります。
経営業務の管理責任者は、基本的には会社の役員又は個人事業主としての経営経験が必要です。
しかし、会社の部長や執行役員など経営者に準ずる地位において経営経験を有する方も存在します。そしてこういった地位にあった方が建設業許可申請することができるのかどうか?そして、その場合どういった資料を提出する必要があるのかご相談を多数頂きます。
以下、東京都の建設業許可申請において求められる資料等をご案内致します。
経営業務管理責任者に準ずる地位にあることを確認するための書類
- 組織図 ※その他これに準ずる書類
業務執行を行う特定の事業部門が、許可を受けようとする建設業に関する事業部門であることを確認するための書類
- 業務分掌規程 ※その他これに準ずる書類
取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として専任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類
- 定款
- 執行役員規程
- 執行役員分掌規程
- 取締役会規則
- 取締役会就業規則
- 取締役会議事録
- その他上記に準ずる書類
各経験の期間を確認するための書類
- 請負契約の締結その他法人の経営業務に関する決議書
- その他上記に準ずる書類
- 契約書など
その他
- 登記簿謄本
- 建設業許可通知書
- 略歴書
以上が東京都が求める経営者業務管理責任者に準ずる地位に基づく確認資料となります。
ご覧頂くと分かると思いますが、ハードルはかなり高いと言えます。
通常、大企業でもない限り、業務分掌規程や役員規定・就業規則などを作成している会社は滅多にありません。また、登記の変更等でもない限り、取締役会議事録の作成などしませんし、ましてや取締役会議事録に部長が出席したことを証明するための署名・押印などしません。
組織図の準備は容易と言えますが、上記各種規定の準備と提出が非常に難しいです。また、これらを提出したところで、最終的には審査担当が総合的に判断して経営業務管理責任者に準ずる地位なのかどうかを判断しますので、申請前の段階で断定的に経営業務管理責任者に準ずる地位であると判断することはほぼ不可能と言えます。
どうしても、経営業務管理責任者に準ずる地位での建設業許可申請を試みたい場合は、まずは建設業課の審査担当にご相談されることをお勧めします。
電話での相談では一般的な回答に留まりますので、上記資料を集めた上で、直接窓口でご相談されることをおすすめします。
因みに、上記経営業務管理責任者に準ずる地位により申請受理されるケースは年間数件です。
専任技術者とは(要件等)
専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。
専任技術者になるための要件
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに該当する者
- 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
- 建築士、施工管理技士などの国家資格を有する者
- 学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者
- 所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者
など
専任技術者の確認資料 ※提出が必要です
現在の常勤性を証明するもの
- 健康保険被保険証の写し(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険証)
但し、国民健康保険証など事業所名が印字されていない場合は、さらに以下のいずれかの資料が必要になります。
- 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し又は健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
- 確定申告書 法人の場合は表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
- その他常勤が確認できるもの ※新規設立会社の場合は、「常勤誓約書」で足りる(東京都の場合)。
実務経験の内容を確認するもの
- 国家資格等を持っている場合は、合格証、免許証等の写し(原本提示)
- 技術者の要件が大臣特認の場合は、その認定証の写し(原本提示)
- 技術者の要件が実務経験の場合は以下の2つの要件をクリアすること
- 実務経験の内容を確認できるものとして次のいずれか
- 実務経験証明期間の常勤(又は営業)を確認できるものとして次のいずれか
・実務経験証明者が建設業許可を有している(いた)場合は、建設業許可申請書・変更届出書の写し(原本提示)
※手引き上は上記建設業許可申請書や変更届出書の写しが必要とありますが、証明者が建設業許可を有している場合は、審査担当側でそれを把握することができるため、許可番号と許可業種のみ分かれば、添付は不要。
・実務経験証明者が建設業許可を有していない場合は、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の写し)
※請求書の場合は、請求金額が入金されたことを確認するための資料として通帳の写しを提出する必要があります(原本提示)。通帳を紛失された場合は、取扱金融機関から取引明細を期間分発行して頂ければ通帳の替わりになります。但し、金融機関によっては、過去数年分までしか発行出来ない場合もありますので、取扱金融機関に事前に確認して下さい。
※発注書のコピーなどで、従前の会社から原本を借りることができない場合、予め審査担当に相談の上、コピーのみで受理して頂けるケースもございます。
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)
・厚生年金被保険者記録照会回答票(事業所名が記載されていること)
・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し(原本提示)又は住民税特別徴収切替申請書の写し(原本提示)
・確定申告書 法人の場合は役員に限って、表紙と役員報酬明細の写し(原本提示)・個人の場合は第1表と第2表の写し(原本提示)
※上記はあくまでも一例です。その他の確認資料により証明することも可能ですので、まずはご相談下さい。
建設業許可申請に必要な書類等
建設業許可申請には下記のような書類の作成と提出が必要になります。
また、下記一覧とは別に経営業務の管理責任者と専任技術者の常勤性などを示すための書類等の添付も必要となります。
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 修業証明書、資格認定証明書の写し、実務経験証明書 ※必要に応じて
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者等・管理技術者一覧表
- 許可申請者の略歴書
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の略歴書
- 定款
- 株主調書
- 財務諸表(直前1期分)
- 履歴事項全部証明書
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名
行政書士に依頼すれば建設業許可は簡単に取れる?
建設業許可の取得は、お客様の状況によって難易度が大きく異なります。要件とそれを証明する書類が全て揃っていれば、行政書士にとってはそれ程難しいものではなく、ご依頼頂ければまず許可を取得することは可能と言えます。
しかし、お問い合わせ頂くお客様のほぼ7,8割は要件が整っていなかったり、要件を証明するための書類が足りなかったりします。
要件が全く満たせない場合は、どの行政書士に依頼しても許可取得は不可能です。その場合は、今後どうすれば要件を満たすことが出来るかをアドバイス致しますので、要件が満たされるまで暫く待って頂くこととなります。
要件は満たせそうだが、それらを証明する書類が揃わないという場合、これはまだ可能性は十分にあります。
あくまでもお客様目線で証明書類が揃わないと思っていても我々行政書士が細かくチェックすれば証明書類が揃う場合が多々あります。
また、行政書士は様々な建設業許可の申請経験から手引き等には記載されていない証明方法を知っているので、建設業許可取得を諦めていた方やこれから取得を検討されている方は、まず行政書士にご相談頂くことをおすすめ致します。
電気工事業者は建設業許可以外の届出も必要です
電気工事業を営もうとする電気工事事業者は、電気工事業法の規定に基づき経済産業大臣又は都道府県知事に登録等の手続をしなくてはなりません。
本手続は建設業許可とは全く別の手続になり、登録・届出を怠ると罰則もありますので注意が必要です。
実務上は、多くの電気工事業者が届出を怠っているのが現状ですが、登録等を怠っていることを気付いた時点でお早目に手続されることをおすすめします。
建設業許可を有している場合と有していない場合とで手続が異なり、一般用電気工作物のみ又は一般用・自家用電気工作物を営もうとする建設業許可を有していない方は「登録電気工事業者」としての届出が必要になり、建設業許可を有している方は「みなし登録電気工事業者」としての届出が必要になります。
自家用電気工作物のみを営もうとする建設業許可を有していない方は「通知電気工事業者」としての届出が必要になり、建設業許可を有している方は「みなし通知電気工事業者」としての届出が必要になります。
登録電気工事業者は、一度手続をすればそれっきりというわけではなく、5年間の有効期間がありますので、期間満了の際は更新の手続をする必要があり、その他にも会社組織や建設業許可の内容等が変更された場合も併せて変更の手続が必要となります。
相談員に断られても諦める必要はありません
都庁や県庁には行政書士が相談員として建設業許可に関する相談を受け付けておりますが、相談員にご相談されて建設業許可申請は不可能と言われてしまい困ってしまっている方がいるかと思います。
しかし、相談員に断られても建設業許可申請できるケースは多数存在します。
相談員は基本的に建設業許可申請の手引きに記載のある原則的なお話に基づいてアドバイスするのみですので、例外的な方法による建設業許可申請まではアドバイスしません。
例外的な方法による建設業許可申請は、基本的に審査担当の判断に寄る部分と申請当事者の交渉能力に寄るところが大きいので、相談員が例外的な方法による申請は可能ですよとは言えないのです。
しかし、手引きに記載のない例外的な申請は多数存在し、実際に許可は下ります。
建設業許可申請において、経営業務の管理責任者と専任技術者の要件確認資料の提示が一番困難と思われますが、
これらも手引きに記載のない補てん資料を活用することで申請することは可能です。
例えば、専任技術者実務経験10年による建設業許可申請を試みる場合、実務経験証明期間の常勤確認資料として以下のいずれかの資料を提出する必要があります。
など
個人事業主を10年以上されていた方などは確定申告書を10年分提出するケースが多いですが、どうしても10年前のものが紛失していて見付からない。その場合、相談員に相談しても原則として確定申告書がなくては申請できないという回答しか得られず、建設業許可申請を諦めなくてはならないと思いがちですが、このようなケースでも建設業許可申請は可能なのです。
例えば、事業を10年前に間違いなく行っていたことが証明出来れば良い訳ですから、発注書や請求書(請求書の場合は通帳が必要)を通常年間3件分~4件分程提出する必要がありますが、これらの数を増やし、かつ、他の注文者やお客様から御社宛に送られてきた請求書や納品書、その他契約書を多数提出することで確定申告書の替わりになることもあります。
但し、一概に上記のケースにおいて上記方法で必ず申請が通るかどうかは個別のケースに寄りますので、他の要件部分の証明が甘ければ申請が通らないことも十分にあります。最終的には全体的な内容を鑑み総合的に判断することになりますので、一部分のみ補てんしたところで難しいケースも多数あります。
ここで説明したいのは、上記のような例外的方法を個別に紹介する訳ではなく、これまできちんと事業を行ってきたにも関わらず、資料が揃わず申請を諦めてきた方や、相談員に不可能と判断されて諦めてきた方にも申請可能性があるということをお伝えしたいのです。
例外的な方法による建設業許可申請は非常にハードルが高いですが、これまで諦めていた建設業許可が取得出来るのですから、試みてみる価値はあるかと思います。
弊所では建設業許可申請に関するご相談は無料で受け付けておりますので、お困りのお客様は遠慮なくご連絡下さい。
無許可業者との請負契約は違法です
建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)を除いて、建設工事は建設業法第3条に基づき建設業許可を受けなくてはなりません。
発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人でも工事を受注して施工する場合は、法人個人問わず建設業許可を受けることが必要になります。
また、建設業許可を受けていない業者と下請負契約を締結した業者も建設業法違反となります。
従って、下請負契約を締結する場合は、契約相手が建設業許可を有する確認する必要があります。
例えば、あなたの会社が下請会社として建設業許可を有していたとしても、元請負会社が建設業許可を有しておらず、建設業許可が必要な工事を受注した場合は、元請・下請いずれの会社も建設業法違反となり、あなたの会社は監督処分の対象となります。
建設業許可を受けずに建設業を営む会社3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられますので、ご注意下さい。
許可がなくても請負える軽微な建設工事
建築一式工事以外の建設工事
- 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
建築一式工事で下記のいずれかに該当する者
- 1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
- 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額
解体工事業登録申請について
解体工事業とは、建設業のうち、建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業を言います。その請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものも含みます。
解体工事は営もうとする事業者は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業登録が必要な事業者
解体工事を営もうとする事業者は、元請・下請の区別にかかわらず、解体工事業を行おうとする区域を管轄する知事の登録をしなければなりません。
営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。
解体工事業の登録が必要でない場合
「土木工事」「建築工事」「解体工事」の建設業許可を受けている事業者は解体工事業の登録の必要はありません。
但し、請負金額が500万円以上の解体工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要となります。
建設業法の改正に伴う解体工事業の申請に関する経過措置は終了したため、2019年6月1日以降は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を受けていたとしても、解体工事を施工することはできないこととなりました。
登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を行う場合は、有効期間満了の2か月前から30日前までに更新手続をする必要があります。
登録手数料
行政に納める手数料は以下のとおりです。
- 新規登録手数料 45,000円
- 更新登録手数料 26,000円
- 変更・廃業等について手数料は発生しません
申請に必要な書類
- 解体工事業登録申請書
- 誓約書
- 実務経験証明書 ※必要に応じて
- 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票など
解体工事業登録申請代行サービス
| サービスプラン | 申請区分 | 登録手数料(法定費用) | 報酬(税込) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 解体工事業登録申請代行サービス | 新規申請 | 45,000円 | 55,000円 | 100,000円 |
| 更新申請 | 26,000円 | 44,000円 | 70,000円 |
社会保険加入の義務化・確認資料について
社会保険等未加入企業に対する取り組み
令和2年10月以降については「適切な保険に加入していること」が許可要件となりました。
従って、令和2年10月1日以降の申請(更新含む)については、適切な社会保険に加入していない場合は、建設業許可を取得することが出来なくなりましたのでご注意下さい。
社会保険加入義務のある営業所(適用事業所)とは
健康保険・厚生年金については、法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
雇用保険については、労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)が適用事業所に該当します。
確認資料
健康保険及び厚生年金の加入を証明する資料
事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記いずれかの資料(写し)
(a)健康保険(全国健康保険協会)加入の場合
- 納入告知書 納付書、領収証書
- 保険納入告知額・領収済通知書
- 社会保険料納入確認(申請)書(受付印のあるもの)
(b)組合管掌健康保険に加入の場合
- (健康保険について)健康保険組合発行の保険料領収証書
- (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
国民健康保険に加入の場合
- (厚生年金保険について)上記(a)のいずれか
雇用保険の加入を証明する資料
- 労働保険概算・確定保険料申告書の控え(又は労働保険料等納入通知書)及びこれにより申告した保険料納入にかかる領収済通知書
建設国保に加入している場合
法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)であっても、健康保険の被保険者となるべき従業員が年金事務所長の承認を受けて建設業にかかる国民健康保険組合に加入している場合は、適用除外です。
建設業許可取得をご検討されている方は遠慮無くお問い合わせ下さい!

代表行政書士 山下 剛芳(やました たけよし)
日本行政書士会連合会 東京行政書士会所属
東京都渋谷区笹塚1-56-6 笹塚楽ビル6F
TEL 03-6666-1855/FAX 03-4333-0254
電話受付時間 10時~19時まで(土日祝日休み)
E-mail :
事務所総合サイト : http://www.usolution.jp/